「保険で白い歯にできるのは何番まで?」という疑問を持つ方は多いでしょう。特に保険適用のCAD/CAM冠などを考えている方にとっては、どの歯まで適用されるのかが重要なポイントになります。本記事では、保険で白い歯(ハイブリッドレジン冠やCAD/CAM冠)にできる歯の範囲について詳しく解説します。
1. 保険で白い歯にできる条件とは?
日本の健康保険制度では、審美性だけを目的とした治療は保険適用外となることが多いですが、一部の条件を満たせば白い歯にすることが可能です。具体的には、ハイブリッドレジン冠やCAD/CAM冠が適用されるケースが増えています。
主な適用条件
- 銀歯ではなく白い歯にすることで機能的なメリットがある場合
- 咬合(かみ合わせ)に問題がない範囲での使用
- 一定の歯の範囲に限定される
2. 何番の歯まで白い歯にできるのか?
歯科の番号は一般的に前歯を1番とし、奥に向かって数えていきます。保険適用の白い歯が可能な範囲は以下の通りです。

① 前歯(1~3番)
前歯(中切歯・側切歯・犬歯)は、保険適用でハイブリッドレジン冠などの白い被せ物を選ぶことができます。前歯は審美的な影響が大きいため、比較的早い段階から保険適用が進められました。
② 小臼歯(4~5番)
小臼歯(第一小臼歯・第二小臼歯)は、CAD/CAM冠を使うことで保険適用の白い歯が可能です。2024年の制度改正により、白い歯の適用範囲が広がりました。
③ 大臼歯(6~7番)
大臼歯(第一大臼歯・第二大臼歯)については、2020年の改正で「上下左右の第一大臼歯(6番)」にもCAD/CAM冠が保険適用となりました。
ただし、7番(第二大臼歯)は基本的に保険適用外です。つまり、通常の条件では7番の歯には銀歯(メタルクラウン)が保険適用される形になります。
3. 適用範囲の例外について
大臼歯(6番や7番)においても、強い金属アレルギーを持っている場合は例外として白い歯の適用範囲が広がります。金属アレルギーと診断されると、第二大臼歯(7番)にもCAD/CAM冠が保険適用されることがあります。
4. 保険適用の白い歯のメリットとデメリット
メリット
- 見た目が自然で銀歯よりも審美性が高い
- 金属を使わないため金属アレルギーのリスクがない
- 保険適用なので比較的安価で治療できる
デメリット
- 耐久性が金属よりも劣るため、割れたりすり減ったりする可能性がある
- 咬合力が強い人には適さないことがある
- 適用範囲に制限がある
5. 自費治療との違い

保険適用の白い歯は基本的にハイブリッドレジンやCAD/CAM冠ですが、自費治療ではより耐久性が高いセラミック冠やジルコニア冠を選ぶことができます。保険適用のものと比べると費用は高くなりますが、
- 耐久性が高い(割れにくく、すり減りにくい)
- 変色しにくい(レジン系は経年劣化で黄ばみやすい)
- 適用範囲に制限がない(7番の奥歯にも使用可)
といったメリットがあります。
まとめ
保険で白い歯にできるのは基本的に 前歯(1~3番)、小臼歯(4~5番)、第一大臼歯(6番) までです。第二大臼歯(7番)は原則として保険適用外ですが、金属アレルギーの診断を受けると例外的に適用されることもあります。
審美性を重視しつつ、費用を抑えたい場合は保険適用の白い歯を選ぶのも良いですが、耐久性や美しさを求めるなら自費治療も検討すると良いでしょう。
歯の健康と見た目のバランスを考えて、最適な治療を選んでください!

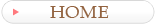
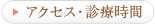
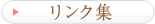


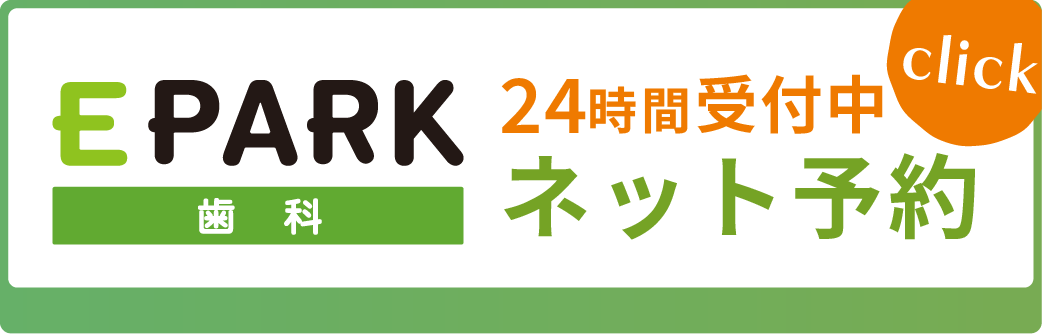

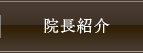
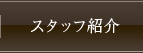
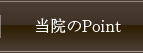
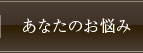
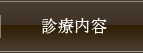
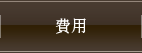
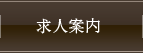

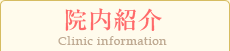


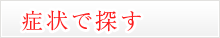
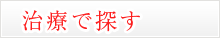



 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら