歯を抜いた後、傷がふさがるまでの期間は数週間から数ヶ月ですが、完全に歯肉が元の状態に戻るまでには1年近くかかることがあります。なぜそんなに時間がかかるのか、不思議に思う人も多いでしょう。実は、歯を抜いた後の治癒は単純な「傷の回復」ではなく、骨や組織の変化が関係する複雑なプロセスなのです。本記事では、その理由を詳しく解説します。
1. 抜歯後の治癒プロセスは段階的に進む
歯を抜いた後、口の中では次のような段階を経て回復していきます。
① 血餅(けっぺい)ができる(1~2日)
抜歯後、傷口には血がたまり、血餅(かさぶたのようなもの)が形成されます。これは傷口を守り、正常な治癒を進めるために重要です。この血餅が剥がれると「ドライソケット」と呼ばれる痛みを伴う状態になることがあります。
② 炎症反応と組織修復(1~2週間)
血餅の下で歯肉や骨の修復が始まります。最初の1~2週間は、炎症反応によって白血球が細菌を排除し、細胞が新しい組織を作り始める時期です。
③ 歯肉の再生(1~2ヶ月)
歯を抜いた穴の周りの歯肉が盛り上がり、徐々に傷口を覆います。見た目は回復したように見えますが、まだ内部の骨の回復は不完全です。
④ 顎の骨の吸収と再構築(6ヶ月~1年)
歯を支えていた顎の骨は、歯がなくなると徐々に吸収され、形を変えていきます。この骨の再形成には長い時間がかかり、完全に安定するまでには1年ほどかかることがあります。

2. なぜ治癒に1年近くかかるのか?
抜歯後の傷がふさがるだけなら1~2ヶ月で完了しますが、「完全に治る」には1年近くかかる理由を詳しく見ていきましょう。
① 顎の骨のリモデリングが必要
抜歯後、歯を支えていた骨は不要になり、体はそれを吸収しようとします。この「骨の吸収」が進むと、周囲の骨が再構築され、新しい形に適応します。このリモデリングには半年から1年ほどかかります。特に高齢者や骨の代謝が遅い人は時間がかかる傾向があります。
② 口の中の環境は治癒を遅らせる要因が多い
口の中は常に唾液や食べ物の影響を受けるため、他の部位の傷よりも治りにくいです。また、食事の際に傷口に刺激が加わったり、細菌が多い環境のため、完全な回復には時間がかかります。
③ 体質や健康状態による影響
糖尿病や喫煙習慣がある人は、血流が悪くなり、歯肉や骨の治癒が遅れることが知られています。また、栄養不足やストレスも回復を遅らせる原因となります。
3. 抜歯後の治癒を早める方法
抜歯後の治癒をスムーズに進めるためには、次のようなポイントを意識しましょう。
① 血餅を守る(抜歯直後~1週間)
血餅は傷口の治癒に不可欠なので、以下のことに注意しましょう。
- 強いうがいをしない
- ストローで飲み物を飲まない(吸う力で血餅が取れる可能性がある)
- 固いものや刺激物(辛いもの・熱いもの)を避ける
② 口腔ケアを徹底する
傷口に細菌が増えると治癒が遅れるため、優しく歯磨きをし、歯科医の指示に従ってうがい薬を使うことが重要です。
③ 栄養バランスの良い食事をとる
タンパク質やビタミンC、カルシウムを含む食事を摂ると、組織の修復が促進されます。特に、骨の回復にはカルシウムとビタミンDが必要です。
④ 禁煙する
喫煙は血流を悪化させ、治癒を遅らせる原因になります。少なくとも抜歯後1週間は禁煙することが望ましいですが、できれば完全に禁煙するのがベストです。
⑤ 適度な運動と睡眠を確保する
血流を促進し、免疫力を高めるために、適度な運動や十分な睡眠を心がけましょう。
4. もし治りが遅いと感じたら?
抜歯後、次のような症状がある場合は、歯科医に相談することをおすすめします。
- 2週間以上経っても痛みが強い → ドライソケットの可能性
- 傷口が膿んでいる、悪臭がする → 感染の可能性
- 半年以上経っても歯肉がへこんでいる → 骨の回復が不十分な可能性
治癒が遅れる原因としては、感染症、糖尿病、栄養不足などが考えられるため、気になる場合は歯科医院を受診しましょう。
5. まとめ
歯を抜いた後、表面の傷がふさがるのは1~2ヶ月ですが、完全に骨が安定するまでには1年ほどかかることがあります。その理由は、顎の骨のリモデリングに時間がかかること、口の中の環境が治癒を遅らせやすいこと、体質や生活習慣が影響することにあります。
回復を早めるためには、血餅を守ること、口腔ケアを徹底すること、栄養バランスの良い食事をとることなどが重要です。もし治りが遅いと感じたら、早めに歯科医に相談しましょう。
抜歯後の適切なケアを行い、スムーズに治癒を進めていきましょう!

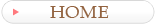
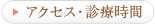
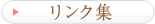


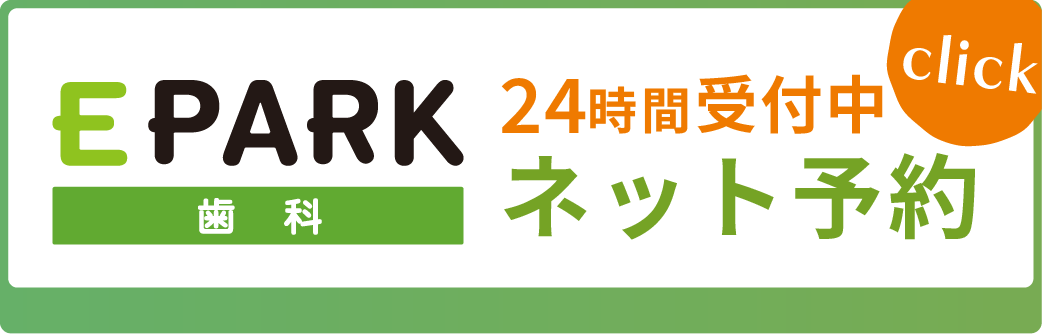

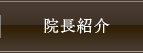
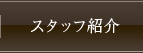
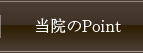
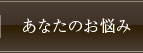
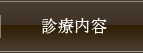
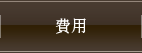
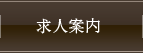

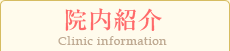


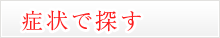
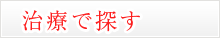



 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら