日常生活の中で無意識に歯を食いしばっていることはありませんか?スポーツをしているときや、重い物を持ち上げるとき、さらにはストレスを感じたときなど、私たちは自然と歯を食いしばることがあります。しかし、この「しょっちゅう歯を食いしばる」行為が習慣化すると、口腔内や全身にさまざまな弊害を引き起こす可能性があります。本記事では、歯を頻繁に食いしばることによる影響や、それを防ぐための対策について詳しく解説します。
1. 歯を食いしばることの主な原因
ストレスや緊張
日常のストレスや緊張が原因で、無意識に歯を食いしばることがあります。特に仕事中や勉強中、プレッシャーを感じる場面では、顎に力が入ることが多いです。
スポーツや運動時の習慣
運動選手は力を発揮するために歯を食いしばることがよくあります。短時間であれば問題ありませんが、これが習慣化すると、歯や顎に負担をかけてしまいます。
噛み合わせの問題
歯並びや噛み合わせが悪いと、無意識のうちに歯を強く噛みしめてしまうことがあります。特に、上下の歯が適切に噛み合っていない場合、特定の部位に過剰な負荷がかかることがあります。
無意識のクセ(歯ぎしり・ブラキシズム)
睡眠中に歯を食いしばる「歯ぎしり」も、慢性的な問題を引き起こす原因の一つです。自覚がないため気づきにくく、長期間続くと歯や顎に深刻なダメージを与えます。
2. 歯を食いしばることによる主な弊害
① 歯へのダメージ
強い力で歯を食いしばることで、歯にひびが入ったり、すり減ったりするリスクがあります。これにより、知覚過敏の原因にもなり得ます。
② 顎関節症のリスク
長期間にわたり歯を食いしばることで、顎関節に負担がかかり、「顎関節症」を引き起こす可能性があります。顎の痛みや開閉時の違和感、音が鳴るなどの症状が現れることがあります。
③ 頭痛や肩こりの原因に
歯を食いしばると、顔や首の筋肉に過剰な緊張が生じ、それが頭痛や肩こりの原因になります。特に、慢性的な緊張状態が続くと、全身のバランスが崩れ、さらなる健康問題を引き起こす可能性があります。
④ 歯茎や歯周組織への悪影響
強い力が歯にかかることで、歯の根元や歯茎に負担がかかります。これにより歯周病が進行しやすくなったり、歯がぐらついたりすることもあります。
⑤ 見た目への影響(エラ張り・顔の歪み)
顎の筋肉が過度に発達すると、エラが張って見えることがあります。また、片側だけ食いしばる癖があると、顔が左右非対称になりやすく、美容面でも問題が生じることがあります。
3. 歯を食いしばることを防ぐための対策
① ストレス管理を行う
ストレスが原因で歯を食いしばる場合、リラックスする習慣を取り入れることが重要です。深呼吸、瞑想、ヨガなどのリラクゼーション方法を試してみましょう。
② 姿勢を改善する
悪い姿勢が顎に負担をかけ、歯を食いしばる原因になることがあります。デスクワーク時の姿勢を見直し、正しい姿勢を意識することが大切です。
③ マウスピースの活用
歯ぎしりや食いしばりがひどい場合は、歯科医院で「ナイトガード(マウスピース)」を作成してもらうのも有効です。これにより、歯や顎へのダメージを軽減できます。

④ 口周りの筋肉をリラックスさせる
意識的に口を開いてリラックスする時間を作ることで、顎の緊張を解放できます。また、ガムを噛むなどして適度に顎を動かすことも有効です。
⑤ 噛み合わせのチェック
歯科医院で噛み合わせの検査を受けることで、食いしばりの原因が噛み合わせにあるのかを確認できます。必要に応じて矯正治療を行うのも一つの方法です。
⑥ 「舌の正しい位置」を意識する
正しい舌の位置は「上あごに軽くつける」ことです。舌を正しく置くことで、歯を無意識に食いしばるのを防ぐことができます。
4. まとめ
しょっちゅう歯を食いしばることは、歯の損傷、顎関節症、頭痛、肩こりなど、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。その原因としては、ストレス、運動習慣、噛み合わせの問題などが考えられます。
予防するためには、ストレス管理、姿勢の改善、マウスピースの使用、噛み合わせの調整、筋肉のリラックスを意識することが大切です。歯を食いしばる癖があると感じたら、早めに対策を講じて、健康的な口腔環境を維持しましょう。
自分では気づきにくい問題だからこそ、定期的に歯科医院でのチェックを受けることもおすすめです。

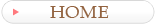
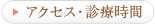
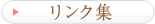


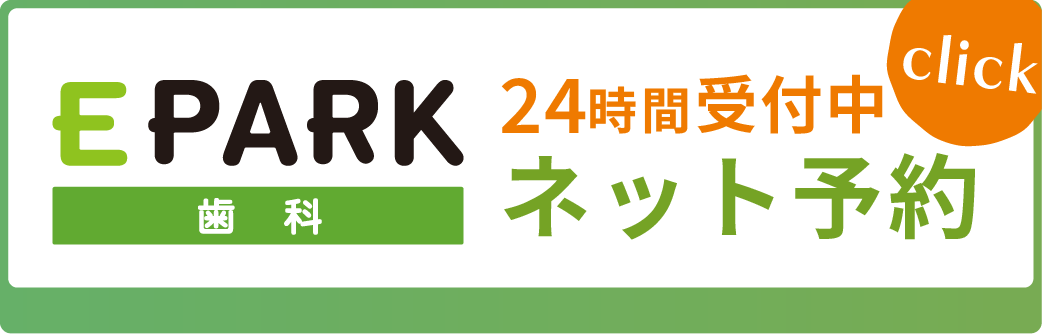

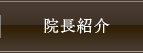
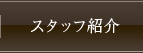
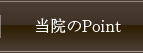
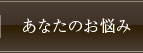
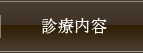
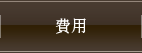
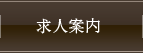

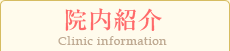


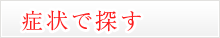
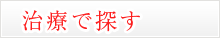



 当院のInstagramはこちら
当院のInstagramはこちら